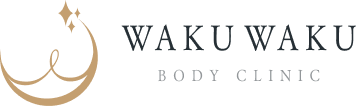産後のむくみに悩むママへ|原因から解消方法、予防策まで徹底解説
「出産を終えてホッと一息つきたいのに、なんだか脚や顔がパンパン…」
産後のむくみは、多くのママが経験する悩みの一つです。
慣れない育児に奮闘する中で、むくみの不快感はさらにストレスを増幅させてしまいますよね。
今回は、産後のむくみに焦点を当て、その原因から効果的な解消方法、そして日々の生活でできる予防策までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、あなたはむくみのメカニズムを理解し、具体的な対策を講じることができるでしょう。
ぜひ、最後まで読んで、産後のむくみをスッキリ解消し、快適な育児ライフを送るための一歩を踏み出してください。
1.なぜ?産後にむくみが起こる主な原因
産後のむくみは、妊娠中から出産にかけての体の変化や、その後の生活習慣などが複合的に影響して起こります。
主な原因として以下の点が挙げられます。
ホルモンバランスの急激な変化:
妊娠中は、女性ホルモンであるエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が大幅に増加しますが、出産後には急激に減少します。このホルモンバランスの急激な変化が、体内の水分調節機能に影響を与え、むくみを引き起こすことがあります。
妊娠中の水分貯留:
妊娠中、体は出産や授乳に備えて通常よりも多くの水分を蓄えます。出産後、この余分な水分が排出される過程で、一時的にむくみとして現れることがあります。
子宮の収縮と血行不良:
出産後、子宮は徐々に元の大きさに戻ろうと収縮しますが、この収縮が一時的に下半身の血管を圧迫し、血行不良を引き起こすことがあります。血行が悪くなると、老廃物や余分な水分が滞りやすくなり、むくみにつながります。
骨盤の歪み:
妊娠や出産によって骨盤が歪むと、全身のリンパの流れや血行が悪くなることがあります。骨盤の歪みは、特に下半身のむくみに影響を与えやすいと考えられています。

運動不足と筋力低下:
産後は、赤ちゃんの世話に追われ、なかなか自分のための時間を確保することが難しくなり、運動不足になりがちです。また、妊娠中に体重が増加し、出産によって筋力が低下することも、むくみを助長する要因となります。
睡眠不足と疲労:
夜間の授乳や赤ちゃんのお世話で睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが乱れ、血行不良やリンパの流れの滞りを引き起こしやすくなります。疲労も同様に、体の機能を低下させ、むくみにつながることがあります。
食生活の変化:
産後は、栄養バランスが偏った食事になりがちです。塩分の摂りすぎや、カリウムやマグネシウムなどのミネラル不足も、むくみの原因となることがあります。

2.産後のむくみ、いつまで続く?その期間と注意点

「このむくみ、いつまで続くんだろう…」と不安に感じているママもいるかもしれません。
産後のむくみの期間には個人差がありますが、一般的には産後2週間から1ヶ月程度で徐々に落ち着いてくることが多いです。
しかし、以下のような場合は注意が必要です。
急激な体重増加を伴うむくみ:
妊娠高血圧症候群などの合併症の可能性も考えられます。
片足だけが極端に腫れる、痛みを伴うむくみ:
深部静脈血栓症の可能性も否定できません。
むくみ以外に、息切れや動悸、胸の痛みなどを伴う場合:
心臓や腎臓の病気の可能性も考えられます。
これらの症状が見られる場合は、自己判断せずに、早めに医療機関を受診するようにしてください。
3.もう悩まない!産後のむくみを解消するための7つの方法
産後のむくみを少しでも早く解消し、快適な毎日を取り戻すために、今日からできる具体的な方法を7つご紹介します。
1. 適度な運動とストレッチで血行促進
無理のない範囲で体を動かすことは、血行を促進し、むくみ解消に効果的です。
ウォーキング:
赤ちゃんと一緒にお散歩に出かけるのも良いでしょう。
軽いストレッチ:
股関節や足首をゆっくりと回したり、アキレス腱を伸ばしたりするストレッチは、下半身の血行を促進します。
産褥体操:
産後1ヶ月健診で医師の許可を得てから、無理のない範囲で産褥体操を取り入れてみましょう。
2. マッサージとリンパドレナージュ
優しくマッサージすることで、滞った水分や老廃物の排出を促し、むくみを軽減できます。
足のマッサージ:

足首からふくらはぎ、太ももにかけて、下から上に向かって優しくさすり上げます。
リンパドレナージュ:
リンパの流れに沿って、軽く圧をかけながらマッサージします。鼠径部や膝裏、足首など、リンパ節のある部分を意識して行うとより効果的です。
3. 弾性ストッキングや着圧ソックスの活用

弾性ストッキングや着圧ソックスは、足に適度な圧力を加えることで、血液やリンパ液の流れをサポートし、むくみを軽減する効果が期待できます。
日中用と夜用を使い分ける:
日中は日中用の、就寝時は就寝時用の圧力が弱いものを選ぶと良いでしょう。
サイズに合ったものを選ぶ:
サイズが合っていないと、効果が得られないだけでなく、血行不良を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
4. バランスの取れた食事と水分補給
食生活の見直しは、むくみ解消の基本です。
塩分を控える:
塩分の摂りすぎは、体内の水分量を増やし、むくみを悪化させる原因となります。
カリウムを積極的に摂取する:
カリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、水分バランスを整える働きがあります。ほうれん草、バナナ、アボカドなどに多く含まれています。
マグネシウムも大切:
マグネシウムは、血行促進や筋肉の緩和に役立ちます。ナッツ類、海藻類、大豆製品などに含まれています。
こまめな水分補給:

水分不足は、血液をドロドロにし、血行不良を招く可能性があります。こまめに水分を補給し、老廃物の排出を促しましょう。ただし、一度に大量の水を飲むのではなく、少しずつ時間をかけて飲むようにしましょう。
5. 湯船に浸かる
シャワーだけでなく、湯船にゆっくりと浸かることで、全身の血行が促進され、リラックス効果も得られます。
38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分程度浸かる:
熱すぎるお湯は、体に負担をかける可能性があります。
入浴剤を活用する:
マッサージ効果のある入浴剤や、血行促進効果のある炭酸入浴剤などもおすすめです。
6. 休息と睡眠をしっかりとる
疲労や睡眠不足は、自律神経の乱れにつながり、むくみを引き起こしやすくなります。
できるだけ横になる時間を作る:
赤ちゃんが寝ている間など、少しでも時間を見つけて横になり、体を休ませましょう。
質の高い睡眠を心がける:
寝る前にリラックスできる環境を整えたり、カフェインの摂取を控えたりするなど、質の高い睡眠を意識しましょう。
7. 骨盤ケア
骨盤の歪みが気になる場合は、骨盤ベルトを使用したり、骨盤矯正の体操を取り入れたりするのも有効です。
骨盤ベルト:
産後、緩んだ骨盤をサポートし、体の軸を安定させる効果が期待できます。
骨盤矯正体操:
産後1ヶ月健診で医師や助産師に相談し、適切な骨盤矯正体操を教えてもらいましょう。
4.産後のむくみ予防のためにできること
むくみは、日々のちょっとした工夫で予防することができます。
長時間同じ体勢を避ける:
授乳や抱っこなど、同じ体勢が続く場合は、こまめに体勢を変えるようにしましょう。
適度な運動を習慣にする:
無理のない範囲で、ウォーキングやストレッチなどを継続することが大切です。
バランスの取れた食事を心がける:
塩分を控え、カリウムやマグネシウムなどのミネラルを積極的に摂るようにしましょう。
こまめな水分補給を心がける:
水分不足にならないように、意識して水分を摂るようにしましょう。
冷え対策をする:
体が冷えると血行が悪くなり、むくみやすくなります。靴下を履いたり、ブランケットを活用するなどして、体を冷やさないようにしましょう。
5.まとめ|産後のむくみを解消して、笑顔で育児を
産後のむくみは、多くのママが経験する一時的な症状ですが、その不快感は決して小さなものではありません。
今回ご紹介した解消方法や予防策を参考に、ご自身の体調や生活スタイルに合わせて、できることから少しずつ取り入れてみてください。
もし、むくみが長引く場合や、他の症状を伴う場合は、無理せず医療機関を受診してくださいね。
産後の大変な時期だからこそ、少しでも快適に過ごせるように、ご自身の体を大切にしてください。あなたの笑顔が、赤ちゃんの笑顔につながります。
この記事を書いた人
高橋 あい

わくわくボディクリニック 代表 / 結果にこだわるサプリメント開発者
2010年、女性の美容と健康に特化したサロン「わくわくボディクリニック」を創業。
自身の摂食障害によるマイナス22kgの体験をきっかけに、栄養学と腸内環境の重要性に着目した元祖麹菌サプリメント「ノーカウント」を開発。
「ノーカウント」は、ダイエット、美肌、腸活をサポートするサプリメントとして、全国250以上のエステサロン・治療院などで導入されるロングセラー商品へと成長。
美容・健康業界のプロフェッショナルからも高い評価を得ている。
また、2020年には神奈川県の未病スタイルアンバサダーに就任し、食生活改善セミナーや健康イベントなどを開催し、地域住民の健康増進に貢献。
現在も最前線で施術を行いながら、科学的根拠に基づくサプリメントの研究・開発・販売を継続。
美容・健康分野における革新的なアプローチを追求し続けている。