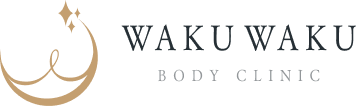立ち仕事してると腰が痛い!腰椎すべり症かも?
腰椎すべり症だと立ち仕事が辛いの??
腰椎すべり症(腰椎すべり症症候群とも呼ばれる)は、腰椎椎間板が変性し、椎骨(腰椎)が前に滑りやすくなる状態を指します。
原因不明ですが、女性の方が男性の5倍、発症しやすいと言われ、一般的な原因は、加齢や姿勢の悪化、運動不足などが挙げられます。
成長期にテニスやゴルフ、野球など、腰をひねる動きが多いスポーツをすることで発症することもあります。
腰椎の基本構造を確認しましょう
腰椎は、人間の脊椎の中で腰部に位置する5つの椎骨からなる部分です。腰椎は上半身の重さを支え、様々な動作や姿勢を可能にする役割を果たしています。

腰椎すべり症は、どのような背骨になっているの?
腰椎すべり症は、腰椎がおなか側にずれるだけの『変性すべり症』と、背骨の一部が分離し、腰椎がおなか側にずれる『分離すべり症』の2つに分けられます。

腰椎すべり症はどんな症状?
腰椎すべり症の主な症状としては以下のようなものが挙げられます。
- 腰痛
腰部やお尻の痛みが一般的です。
- 坐骨神経痛
腰椎の滑りが神経を圧迫し、腰から足にかけての痛みやしびれが生じることがあります。
- 歩行困難
腰椎の滑りが進行すると、歩行に支障をきたすことがあります。 原因としては、加齢による椎間板の変性や、外傷、遺伝的な要因が挙げられます。
また、過度な負担や不適切な姿勢もリスク因子となり得ます。
診断は主に症状や画像診断(X線、MRIなど)を基に行われ、治療法は症状の重症度により異なります。
軽度の場合は安静や理学療法で痛みを管理し、重度の場合には手術が検討されることもありますが手術は最終手段とされることが一般的です。
立ち仕事との関係性はあるの?
- 立ち仕事のせい?
長時間の立ち仕事や、重いものを運ぶお仕事をしている方によくみられる腰椎すべり症。 立っている時や腰を反ったときに痛みが出るケースが多いです。
座っていたり安静にしていたりするときには痛みがでない事が多く、そのために腰椎すべり症になっている事にご自身が気付かない場合があります。
- 立ち仕事をする時に気を付ける事は?
長時間同じ姿勢を続けないこと、そして立っている時は腰に負担がかからない立ち方が出来ているか時々自分でチェックしましょう。
横から見た時に、耳・肩・股関節・膝・くるぶしが一直線になっているか意識することが大切です。

そして立っている時間以外の過ごし方でかなり予防にも痛みの緩和にもなります。
毎日しっかりお風呂に入って血行を良くする・水分をこまめに取る・マッサージやストレッチをこまめにするなどのケアをしましょう。
そして「痛いから動かない」のが続いてしまうと体力が低下してしまいます。
自分で対策できることはあるの?
- おススメのトレーニング
立ち仕事をしているので腰椎すべり症を予防したい!もうすでに痛みが出始めているから改善したい!という方向けのトレーニングをご紹介します。いずれも筋肉の柔軟性アップや血行促進が目標で、痛みやしびれを軽減してくれます。
①水中ウォーキング
水中は浮力の効果で陸上で歩くよりも腰に負担がかかりにくくなります。また、水圧の力で血液の循環がよくなるため血行もよくなります。そして、水の抵抗が全方向からかかるため日常生活で使わない筋肉にも刺激が入り体力アップにもつながります。
まずはゆっくり水中で歩く事から始めてみましょう。前歩き・横歩き・後ろ歩きなど、歩き方を変えれば腰から脚のゆる筋肉のストレッチと強化になります。
高血圧や心臓病の薬を服用している場合は、お医者様と相談しながらトレーニングを始めましょう。
②お腹のインナーマッスル、大腰筋をストレッチする
大腰筋が固くなると、すべり症の腰椎を前側に引っ張る力が強くなります。この筋肉をストレッチすることで、腰椎の負担を減らすことができます。

写真のように片足を前側に曲げ、もう片方の足をなるべく後ろ側に引くようにします。そうすると太腿の前側と、大腰筋がじんわり伸びてくるので、そのままで鼻呼吸を20~30秒続けましょう。
左右同じようにストレッチします。朝起きた時と寝る前にやってみましょう。
③背中をストレッチする
イスに腰掛けます。肘を曲げた状態で腕を前に出し、左右の手の指先を合わせます。息を吐きながら大きな風船を抱えているイメージで5秒かけて背中を丸めていきます。
息をすいながら5秒かけて体を戻します。これを10回繰り返しましょう。 こちらのストレッチも朝と夜にリラックスしながらやりましょう。
- まとめ
腰椎すべり症は立ち仕事をする人々にとって辛い問題ですが、適切な予防策を取ることでリスクを軽減することができます。姿勢の維持や定期的なストレッチで、日々ケアしていきましょう。